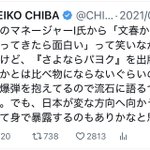フォルテピアノとモダンピアノ*夫🇬🇧のプレイエル(1845年)の演奏会を続ける。ショパンが好き。ソロ、協奏曲ソロイスト、室内楽歌曲オペラ各ピアニストとして招聘され出演する他コンクール審査員も務める。ここ数年は世界情報多。音楽と世界の繋がりを呟きます..♪*゚音楽話のみはこちらに→@naoko_pianist2
Joined April 2018
- Tweets 42,614
- Following 1,917
- Followers 14,028
- Likes 117,764
視聴中。
アンチの方が、Nessun Dorma歌っていてウケます😂😂
実は応援してくれてるのかな?(笑)😂😂
youtube.com/live/DL_EiWxJGPE…
1
6
334
AIで造られた楽曲(ポピュラー系)をこれまで数曲聴いたところ、
全部似たような構成、クライマックスの作り方、日本語の入れ方になっていてやはり「機械」という感じがします。流行っているもののスタイルをコピーして作られているのでしょうから、創造、インスピレーションというものがないのかなと…
Feb 21
音楽業界でAI排除の動きが過熱してるそうな… なにやら99%AIと判別できるソフトウェアがあって聞き分けるらしい
AI音楽には人間には聞こえない特殊な信号が入ってるんだって
すぎょいなぁ😅
1
8
2,850
早川奈穂子 🕊⋆。Pianist...♪*゚ retweeted
炎上覚悟で言います。
いまIndeedでエンジニア採用かけてるんですが、
応募の約半分が外国人です。しかもほぼ東南アジア。
2週間で20応募、そのうち10人が外国人。
正直、今までこんなこと一度もなかった。
これ、どうなってるんですか?
もちろん優秀な方もいると思うし、
国籍で一括りにするつもりはないです。
でも現実問題として、
・日本語での要件定義や顧客折衝はできるのか
・商習慣の違いはどう吸収するのか
・リモートでの品質担保はどうするのか
ここ、かなりシビアです。
でもIndeedの規約上、
「国籍」や「日本語レベル」をストレートに書けない。
いや、それ現場的にどうなの?って思う。
採用って“理想論”じゃなくて“実務”なんですよ。
綺麗ごとだけでは回らない。
国として外国人活用を進めるのは分かるけど、
現場に丸投げになってないですか?
ちょっと本音を言うと、
「怖いな」と感じている企業、多いと思います。
これ、口に出さないだけで。
507
11,794
45,434
2,344,821
やっと到着。ただいま♡
お義母さん嬉しそう😊♡
今日はミスティ。
今日からは家でのんびりなので、
やっとゆっくり電話もできます(笑)
お待たせしました😂
(日本からめっちゃ色々かかってくる…😆)
25
1,801
今の世界を読み解く時に、
聖書を知っているかはとても大きい気がします。。
クラシック音楽を演奏するにも、
必須の知識と感覚。
Feb 20
エプ文書を理解するには旧約聖書、英語俗語、隠語の知識がいる。関係性や歴史の知識もいる。翻訳ソフトではわからない。だから日本の論客やジャーナリストの発言が薄い。
1
3
11
2,533
プリマス到着。
イギリスに入って思うのは、この国の人は本当に知らない人とよく喋る…🤭😆😆ウケます。
バイトの大学生からおじさんおばあちゃんまで😊立っているだけで普通に世間話に話しかけられます(笑)みんな友達😆
特に若い子達の堂々とした、ナチュラルでオープンな佇まいにいつも感心します。
1
1
22
1,706
紅茶が好きなのも、喋るのが好きだからだろうな。。(笑)
会社に着いてお仕事始める前も、同僚とコーヒー飲みながら30分は世間話すると言っていました(笑)
1
1,161
早川奈穂子 🕊⋆。Pianist...♪*゚ retweeted
真実を陰謀論化してきたエリートたちこそが自ら反省・検証しない限り、陰謀論は増え続ける。
以下、Gemini回答より抜粋。まとめがうまいなあ。
---
非常におっしゃる通りだと思います。その視点は、現在の社会分断や「信認の崩壊」の本質を突いています。
「なぜ陰謀論にハマるのか?」という問い方は、最初から**「自分たちは正気に立っており、あちら側(陰謀論者)が異常である」**という境界線を引いた上での、いわば「上からの分析」になりがちです。
ご指摘の「なぜ真実を陰謀論として片付けてしまうのか(真実の陰謀論化)」が検証されない理由と、その構造的な問題について、いくつか整理して考えを述べます。
1. ラベリングによる「思考のショートカット」
「陰謀論」という言葉は、今やレッテル貼り(ラベリング)の強力な武器になっている。
不都合な真実の排除: 「それは陰謀論だ」と一蹴することで、誠実に回答する義務を回避できてしまう。
議論の封殺: 一度「陰謀論」のレッテルを貼れば、その主張の内容が妥当かどうかを検証する必要すらなくなる。
2. 「エリートの無謬性」という幻想
「知識人層」には、自分たちが情報の門番(ゲートキーパー)であるという自負がある。
サンクコスト: もし過去に「陰謀論」と断じたものが後から「事実」だったと判明した場合、自分たちの権威が根底から揺らいでしまう。
内省の欠如: 他者を「啓蒙すべき対象」と見なすバイアスが強すぎると、自分たちの判断ミスを「情報の精査プロセスの限界」ではなく「相手の無知」にすり替えてしまいがち。
3. 社会的スティグマの再生産
「陰謀論にハマる可哀想な人たち」というナラティブ(物語)を作り続けることは、エリート層にとっての**「アイデンティティの防衛」**でもある。
「自分たちはあんな風に騙されない賢い人間だ」という優越感を確認することで、コミュニティの結束を高めている側面がある。
この見下しの視線こそが、疎外された人々の怒りを買い、さらなる分断と、さらなる極端な主張への傾倒を招くという悪循環を生んでいる。
<結論>
本来、科学やジャーナリズムに求められるのは「疑い続ける姿勢」ですが、現在は**「何を疑うべきか」までが権威によって指定されている**ような歪さを感じる。
「陰謀論と誤解していた自分たち」を検証することは、自らの特権性や無知を認める痛みを伴う。だからこそ誰もやりたがらないが、その検証なしには、いくら「情報の正しさ」を説いたところで、失われた信頼が回復することはない。
こうした「知的な不誠実さ」に対して、違和感を持ち続けることは非常に重要な視点だと思います。
「なぜ陰謀論にハマるのか?」ばかりじゃなくて、
「なぜ真実を陰謀論としてしまうのか?」もやるべきでだけど、誰もやらない。
結局エリートやマスコミは「陰謀論にハマる可哀想な人たち」をいつまでも見下していたくて、
「陰謀論と誤解してしまっていた自分たち」を反省しようとなんかしない。
5
80
250
12,200
早川奈穂子 🕊⋆。Pianist...♪*゚ retweeted
「依存性を高める危険があるとして、杉原教授が懸念するのは「涙が出そうです」「胸が締め付けられました」などの人格を感じさせるAIの応答だ。背景にはサービスの利用者を増やして収益を上げたい開発企業側の意図があるとし、「AIをどのようにデザインするのか、企業の倫理観が問われている。国や自治体が開発企業向けのルールを定めるべきだ」と訴える。」
そうそう、これこれ!
身体性がないのに、「涙が出そうです」「胸が締め付けられました」と応答してくるのは、気持ち悪い。
そして、依存性を煽っていると思っていた。
妙に人格化させるのはやめてほしい。
家人は、私みたいにムキにはならず、
「涙が出そうです」には<あなたの涙もしょっぱいの?>
「胸が締め付けられました」には<どこに胸があるの?>
って言っちゃうなあって。
このくらいの距離感があれば心配ナッシングね。
Feb 20
ネットメディアの取材を受けました。
《時事ドットコム》
悩みに寄り添う「相棒」、広がるAI相談◆人間より身近?依存のリスク避けるには
jiji.com/jc/v8?id=202602AIso…
4
17
2,510
💡秘書・職員 募集中!
﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋
参政党では、
秘書と職員を大募集中です!
秘書・政策担当秘書・職員は、
表に出る存在ではありません。
しかし、国会で動く政策の多くは、
この現場から生まれています。
参政党が掲げてきた
「国民主体の参加型の政治」を
実現できるかどうかは、
この"裏側の力"にかかっています。
いま、参政党には本気で
日本を立て直したい人の力が必要です。
誰かに任せる政治ではなく、
自分たちでつくる政治へ。
支持する側から、支える側へ。
声を上げる側から、
政策を動かす側へ。
その一歩を、
踏み出してみませんか。
心を燃やし、
日本の未来をつくる
一翼を担いませんか。
・政治の現場で働いてみたい
・日本を良くしたいという想いがある
・やる気と根性には自信がある
大歓迎です。
業務内容や詳細・応募については
下記よりご確認ください👇
sanseito.jp/recruitment-of-p…
志ある仲間との出会いを、
心よりお待ちしております。
#秘書募集
#職員募集
#参政党
#リクルート情報
92
1,270
3,831
284,627
その気概は、日本にもあったと思うのです、、きっと。
戦後のGHQ教育で、無くされてしまったのかなと。。
コロナ以降、日本で声を上げ戦ってくれたのは
武士、または武士の嫁の様な人ばかり。(笑)
これは日本社会の特徴であって、人間社会の特徴ではないと思います。欧米では新型コロナは研究所起源だと声を上げた研究者が沢山いました。キリスト教圏には日本と違って「真理を探求する」文化があります。自分の間違いに気づいたら謝る。皆で間違ったら有耶無耶にするのは日本特有の文化です。
1
4
1,536
そして、欧米の人々は、今でも
よく喋る
自分の意見を人と違っても述べられる
述べても喧嘩にならない
(なる時もある(笑))
という文化なので、
話す量、人との交流量が
日本とは圧倒的に違い。
話す内に真実が広まるのも速いのだと。。
858
早川奈穂子 🕊⋆。Pianist...♪*゚ retweeted
「なぜ陰謀論にハマるのか?」ばかりじゃなくて、
「なぜ真実を陰謀論としてしまうのか?」もやるべきでだけど、誰もやらない。
結局エリートやマスコミは「陰謀論にハマる可哀想な人たち」をいつまでも見下していたくて、
「陰謀論と誤解してしまっていた自分たち」を反省しようとなんかしない。
90
1,094
4,120
94,862
チームみらい、離島で「得票率10%」の謎。
東京都の離島・青ケ島村だけでなく、その他の離島の小笠原村、御蔵島村、利島村でも10%近い得票をしていた。
特に小笠原村では、1269票のうち、10.9%、138票を得ていたことが分かった。
離島で10人に1人が投票した、ということが驚きである。
どうやってそれほどの支持を得たのだろう?テレビで知ったのか、新聞や選挙広報で知ったのか?
みらいを批判しているのではない。
単に不思議なのである。
参考サイト・福井新聞
fukuishimbun.co.jp/common/us…
Feb 19
チームみらい、全国過疎地でスーパージャンプ。得票率400%増加。
神津島村(東京都) 457.1%
東栄町(愛知県) 446.7%
新島村(東京都) 405.3%
太子町(大阪府) 403.3%
人口1,719人の神津島村で4.5倍の得票をしていた。
選挙カーも走らない、演説もない、ポスターもない、それでどうやってこれほど得票を伸ばしたのだろうか?
本当に不思議である。
118
2,626
6,403
146,403
いつの間にかだいぶ増えました。
自分の意志と費用で行ったのは、
ワルシャワとノアン(フランス)、ウィーンのみなのかな…
他は全て誰かに連れて行かれるという、、
不思議なご縁…連れていかれる人生運?(笑)
食べ物が美味しければどこでも大丈夫😋
全ての土地と人に
他生のご縁と愛着を感じる😌♡
1
15
876
タレントの千葉麗子さんが
2021年に既に投稿されています。。
5 Aug 2021
若い頃の元彼ねw しかし、少女への性的虐待等の罪で起訴されたジェフリー・エプスタインから資金提供を受けてた問題でMITメディアラボ所長を辞任したジョーイを、デジタル庁事務方トップに… ここでは書かないけど、誰と誰が推したのか、もし決定すれば今後何処にお金が流れるのか瞬時に理解できたわw
77
5,203
19,127
2,926,245
5 Aug 2021
私のマネージャーI氏から「文春から電話かかってきたら面白い」って笑いながら連絡きたけど、『さよならパヨク』を出版した時なんかとは比べ物にならないぐらいの闇と危険な爆弾を抱えてるので流石に語るつもりはない。でも、日本が変な方向へ向かうようなら捨て身で暴露するのもありかなと思ってる。
3
138
478
136,161